あらすじ
新潟市の下町。
築四十年の古民家の前で、四人は立ち止まる。
ここに、小さなデイサービスをつくる。
その決断は、理想ではなく覚悟だった。
制度という壁。
融資という現実。
副業という葛藤。
そして、消えない過去の記憶。
これは「希望の家」が生まれる前夜の物語。
壊れた家族が、もう一度支える側へ立とうとする、静かな始まり。
キャラクタープロフィール
主な登場人物
・涼太 ― 古民家をデイサービスに変えようとする中心人物
・真奈美 ― 過去の傷を抱えながら再び支える側へ立とうとする
・圭吾 ― 既存施設の施設長。安定と挑戦の間で揺れる
・亮 ― 慎重派の相談員。副業という立場に葛藤する
プロローグ
初夏の風が、日本海からゆっくりと吹き込んでいた。
新潟市の下町。
信濃川から少し入った古い住宅街の一角に、その家はあった。
築四十年。
木造二階建て。
瓦屋根はところどころ苔むし、縁側のガラス戸には細いひびが走っている。
庭は手入れされぬまま雑草に覆われ、物干し台だけが取り残されていた。
「……ここ、か」
涼太は小さく息を吐いた。
真奈美は、門柱の前で足を止めたまま動かなかった。
――本当に、ここでやるの?
声に出さなくても、その迷いは涼太に伝わっていた。
かつて三世代が暮らしていたというこの家は、
持ち主が亡くなり、数年空き家になっていた。
売却も決まらず、ただ時間だけが流れていた場所。
けれど、涼太には見えていた。
廊下に手すりをつけ、
段差をスロープに変え、
和室を滑りにくい床材に張り替えれば――
ここは、生まれ変わる。
「病院でもない。
大きな施設でもない。
でも、家でもない孤独でもない場所」
涼太は、門扉を押し開けた。
第1章 廃屋の中で
玄関を開けた瞬間、湿った木の匂いが鼻をついた。
古い家の匂い。
長く閉じられていた空気。
少しだけ、黴の混じった畳の匂い。
その匂いが、胸の奥に触れた瞬間――
どくん、と心臓が跳ねた。
真奈美は、無意識に息を止める。
廊下に足を踏み入れたとき、
きしむ音が大きく響いた。
その音が、なぜかあの夜の音と重なる。
――玄関が開く音。
金属の鍵が当たる、乾いた響き。
一瞬で身体が固まった。
涼太は気づかず、部屋の奥を見ている。
真奈美の視界だけが、わずかに揺れた。
きしむ床板。
薄暗い和室。
閉じた空気。
それは、あの頃の家とよく似ていた。
アルコールの匂い。
不規則な足取り。
コップが倒れる音。
怒鳴り声。
「なんでだよ……」
かすれた声が、耳の奥で再生される。
胸が締めつけられた。
息が、浅くなる。
――大丈夫、大丈夫。
頭では分かっている。
ここは違う。
あの家ではない。
涼太は酒に溺れる人ではない。
それでも、身体が先に反応してしまう。
手のひらが冷たくなり、
指先がしびれる。
呼吸が速い。
吸っているのに、入ってこない。
「ここで……デイサービスを?」
声がわずかに震える。
その震えは、未来への不安だけではない。
過去が、まだ終わっていない証拠だった。
畳の上に立った瞬間、
強烈な記憶がよみがえる。
夜中、
健一が座り込んでいた畳。
空き瓶が転がり、
割れたグラスの破片が光る。
子どもたちを背中にかばいながら、
「大丈夫だから」と言い続けた自分。
あのときも、畳の匂いがした。
湿った、重たい匂い。
喉がひりつく。
視界が少し白くなる。
動悸が速い。
耳鳴り。
「……っ」
無意識に胸を押さえる。
涼太が振り向く。
「真奈美?」
声が遠く聞こえる。
違う。
ここは違う。
この人は違う。
でも――
また壊れたらどうする?
頭の奥で、もう一人の自分がささやく。
また忙しくなって、
また支える側になって、
また限界まで我慢して、
また誰にも言えなくなって、
そして、また崩れる?
怖いのは、失敗ではない。
怖いのは――
自分がまた無理をする人間に戻ること。
「私は……もう、戦いたくない」
かすれた声がこぼれる。
涼太は、ゆっくり近づいてくる。
真奈美は気づく。
今の自分の呼吸が荒いことに。
肩が上下していることに。
「大丈夫か?」
その声は低く、静かだ。
怒鳴らない。
責めない。
問い詰めない。
ただ、そこにある。
それだけで、少し呼吸が戻る。
「……畳の匂いが」
自分でも驚く言葉だった。
「昔の家を思い出したの」
涼太は、間を置く。
「思い出していいよ」
その一言で、胸の奥の緊張がわずかに緩んだ。
思い出してはいけないと思っていた。
忘れなければ、前に進めないと思っていた。
でも、忘れなくてもいいのかもしれない。
真奈美は、ゆっくりと膝をつく。
畳に手を置く。
冷たい。
けれど、あの頃の畳とは違う。
ここには怒鳴り声はない。
瓶の割れる音もない。
子どもを守るために立ち塞がる自分もいない。
ただ、静かな空間がある。
「怖い」
正直に言えた。
「また、自分を後回しにしそうで怖い」
涼太は隣に座る。
「後回しにしそうになったら、止める」
「……あなたが?」
「俺も。健太も。亮も」
俺たちが。
その言葉が、ゆっくり胸に入る。
一人で支えなくていい。
それは、理屈では理解していた。
でも、身体が信じるには時間がいる。
真奈美は深く息を吸う。
今度は、ちゃんと空気が入る。
ゆっくり吐く。
心臓の鼓動が、少し落ち着く。
過去は消えない。
匂いも、音も、夜の記憶も。
でも、それは今ではない。
「……少しだけ、やってみる」
震えはまだある。
それでも、逃げる言葉ではなかった。
廃屋の中で、
真奈美は過去と向き合いながら、
それでも未来を選ぼうとしていた。
畳の匂いは、もう敵ではなかった。
それは、
生き抜いた証の匂いだった。
第2章 制度という壁
2-1 理想は、基準を超えられるのか
市役所の介護保険担当窓口は、思っていたよりも静かだった。
静かすぎる、と涼太は思った。
待合の椅子に座ると、自分の鼓動の方がうるさく感じる。
膝の上のクリアファイルが、やけに重い。
中には事業計画書の草案。
だが本当に持ってきたのは、
あの古民家で見た、真奈美の震える横顔だった。
番号が呼ばれる。
「地域密着型通所介護のご相談ですね」
職員は柔らかい口調だったが、言葉は正確で速い。
「定員は十名以下。
管理者は常勤。
生活相談員の資格要件を満たすこと。
機能訓練指導員の配置。
平面図の提出。
消防法適合証明。
運営規程、重要事項説明書。
運営推進会議の設置。」
淡々と列挙される条件。
涼太は頷きながら、心のどこかで別の声を聞いていた。
――古い梁は残せるのか。
――畳は全部撤去か。
――庭の段差はどうなる。
「古民家を改装予定とのことですが、段差はすべて解消が原則です」
「すべて、ですか?」
「はい。転倒事故は重大事故につながります」
転倒。
その言葉に、涼太は一瞬、別の記憶を思い出す。
救急搬送、家族の動揺、謝罪。
制度は、理想を否定しているわけではない。
事故を防ぐための基準だ。
だが、理想のぬくもりは、数字に置き換わっていく。
「浴室は?」
「まだ……検討中です」
「車椅子対応でなければ指定は難しい可能性があります」
難しい可能性。
それは遠回しな「不可」だった。
古民家の浴室は狭い。
拡張には解体が必要。
解体には費用がかかる。
涼太の喉が乾く。
――やる前から、無理なのか?
窓の外の空は灰色だった。
どの階かは分からない。
ただ、街の音が遠い。
「事前相談は何度でも可能です」
職員の言葉は親切だった。
だが、制度は譲歩しない。
外に出た瞬間、風が強く吹きつけた。
日本海側特有の湿った空気が、コートの隙間から入り込む。
理想は、基準を超えられるのか。
いや。
超えるのではない。
合わせなければならない。
それが現実だった。
2-2 善意は、数字に耐えられるのか
銀行の応接室は、暖かすぎるほどだった。
だが涼太の指先は冷えていた。
テーブルの上に並ぶ資料。
・自己資金
・収支予測三年分
・設備投資額
・改修費見積
・人件費シミュレーション
担当者は落ち着いた声で尋ねる。
「初年度の稼働率は?」
「七割を想定しています」
「根拠は?」
一瞬、言葉が止まる。
根拠。
それは「地域に必要だから」では足りない。
「近隣の要介護認定者数と、既存デイの待機状況から…」
声が、わずかに震える。
担当者は続ける。
「改修費が想定より高いですね」
古民家特有の問題。
・床下の腐食
・断熱不足
・配管の老朽化
・耐震補強
見積は当初より百万円以上増えていた。
「自己資金割合が低いと、審査は厳しくなります」
その言葉は、刃のようだった。
真奈美の顔が浮かぶ。
――もう揺らしたくない。
自分の挑戦で、
彼女の平穏を壊すわけにはいかない。
「理念は理解します」
担当者は言う。
「ですが、事業は継続できなければ意味がありません」
善意は、赤字では続かない。
人件費を削る?
看護師を減らす?
浴室改修を最低限にする?
そのどれもが、理念を削る行為に思えた。
沈黙の後、担当者が静かに言う。
「小規模は強みでもあります。固定費を抑えられる可能性もあります。再度、数字を整理しましょう」
拒絶ではなかった。
だが、甘くもない。
銀行を出ると、夕方の風が冷たかった。
善意は、数字に耐えられるのか。
耐えなければならない。
理念を守るために。
2-3 理念は、記録で守れるのか
開設から数ヶ月後。
実地指導の日。
事務室の空気は、朝から張りつめていた。
書類は整えてある。
はずだった。
だが、見返すほどに不安が増す。
「この利用者のアセスメント、更新日は?」
担当者の声は穏やかだ。
「……先月です」
「生活機能の変化は記載されていますか?」
ページをめくる手が、わずかに震える。
記録はある。
だが、理想ほど丁寧ではない。
畑で笑った日。
真奈美と一緒に味噌汁を作った日。
亮が肩を貸して散歩した日。
それは、すべて物語としては確かだった。
だが、制度は物語を評価しない。
「理念に『役割を持てる場づくり』とありますが、具体的な記録は?」
涼太の胸が強く打つ。
「今後、活動記録を様式化します」
それは改善事項だった。
重大な違反ではない。
だが、理念が紙に追いついていない現実を突きつけられる。
さらに指摘が続く。
・運営推進会議の議事録の署名漏れ
・ヒヤリハット報告の分析不足
・研修記録の詳細不足
どれも致命傷ではない。
だが、積み重なれば信頼を失う。
指導が終わった後、
涼太は椅子に崩れ落ちた。
「俺は、理念を守れているか」
呟く。
制度は敵ではない。
だが、甘くもない。
理念は、語るだけでは守れない。
記録し、検証し、改善し続けて初めて守れる。
窓の外は鉛色の空。
冬の匂いがする。
希望の家は、まだ小さい。
だが今日、
制度に否定はされなかった。
揺れながら、立っている。
それが、今の現実だった。
第3章 圭吾の立場
3-1 守る側の責任
緑風園の会議室は、静まり返っていた。
年度末の報告会。
事故報告、稼働率、加算算定状況。
数字は悪くない。
むしろ安定している。
「今年度は大きな指摘もなく、順調でした」
事務長の声が響く。
圭吾は資料に目を落としたまま、頷いた。
順調。
その言葉が、なぜか胸に刺さる。
順調ということは、
波風を立てていないということだ。
理念を守るというより、
基準を守る。
それは悪いことではない。
むしろ施設長として正しい。
だが、頭のどこかで別の光景が浮かぶ。
古民家。
黒光りする梁。
震える真奈美の横顔。
数字に追われながらも、まっすぐ立つ涼太。
――あいつは、揺れながら進んでいる。
会議が終わると、理事長に呼ばれた。
「最近、別法人の立ち上げを手伝っているそうだな」
声は穏やかだが、目は笑っていない。
「助言程度です」
「本業に支障は出ていないか?」
圭吾は一瞬、言葉を選んだ。
「出ていません」
それは事実だ。
だが、心は揺れている。
理事長は続ける。
「施設長は責任のある立場だ。余計な火種は抱えるな」
火種。
希望の家は、火種なのか。
圭吾は頭を下げながら、
自分の胸の奥が、じわりと熱くなるのを感じた。
守る側の責任。
それは、
波を立てないことか。
それとも、
新しい波を生むことか。
3-2 安定は、正しいのか
その夜。
圭吾は車を止めたまま、エンジンを切らずにいた。
フロントガラス越しに見える住宅街。
冬の空は低い。
安定した給与。
法人の信頼。
職員の生活。
施設長という肩書きは、
重いが、守られている。
だが、希望の家は違う。
融資。
指定。
実地指導。
失敗すれば終わる。
亮からメッセージが届く。
「施設長、今日どうだった?」
亮は知っている。
圭吾が揺れていることを。
「順調だ」
そう打って、消す。
「……考え中だ」
送信。
しばらくして、返信が来る。
「施設長が動いたら、現場は変わる。でも、動かなくても責めない」
責めない。
その言葉が重い。
責められない選択は、楽だ。
だが、楽な方が正しいとは限らない。
圭吾は目を閉じる。
希望の家で見た、利用者の笑顔。
畑で土を触る手。
真奈美の、ぎこちないが優しい声。
あの場所は、まだ未熟だ。
制度にも、数字にも、慣れていない。
だからこそ、支えが必要だ。
――辞めるか?
その考えが、初めて具体的になる。
だが、すぐに別の顔が浮かぶ。
緑風園の職員たち。
家庭を持つ若手。
相談に来る利用者家族。
ここを捨てることが、正義なのか。
安定は、逃げか。
それとも責任か。
圭吾は答えを出せないまま、夜の住宅街を見つめていた。
3-3 背負うのは、誰か
数日後。
希望の家の事務室。
実地指導の書類がまだ机に積まれている。
涼太は疲れていた。
顔色が悪い。
「通った。でも、通っただけだ」
ぽつりとこぼす。
圭吾は書類をめくる。
「改善事項は、改善すればいい」
「言うのは簡単だ」
涼太の声は、初めて弱さを帯びていた。
「全部、俺の責任だ。真奈美も、健太も、亮も巻き込んでる」
圭吾は静かに言う。
「違う」
「……何が違う」
「背負うのは一人じゃない」
沈黙。
圭吾は続ける。
「俺はまだ施設長だ。簡単には辞められない」
涼太は目を伏せる。
「分かってる」
「でもな」
圭吾は一歩近づく。
「制度の中にいる人間が、制度の外の挑戦を支えることはできる」
涼太が顔を上げる。
「辞めないのか」
「今は、辞めない」
それは逃げではない。
選択だ。
「だが、関わる。中途半端じゃなく」
圭吾は机の上の運営規程を指差す。
「理念を守るのは、情熱じゃない。構造だ。俺がそこを整える」
涼太の目に、わずかな光が戻る。
「背負うのは、一人じゃない」
その言葉が、事務室に静かに落ちる。
外では、冬の風が鳴っている。
圭吾はまだ施設長だ。
安定側に立ちながら、
揺れている側を支える。
それは、
もっと難しい立場だった。
だが、彼は選んだ。
辞めない。
だが、離れない。
その決意が、
希望の家にもう一つの柱を生んでいた。
第4章 亮の揺れ
4-1 静かな側にいるということ
緑風園の相談室は、いつも穏やかだ。
白い壁。
丸いテーブル。
少し低めの椅子。
利用者の家族が向かいに座り、
不安や愚痴や怒りを置いていく。
亮は頷きながら、言葉を選ぶ。
「お父さまの状態は、確かに変化しています。ただ、今できていることもあります」
声は落ち着いている。
表情も崩れない。
相談員としては、悪くない。
だがその日の帰り道、
亮はふと立ち止まった。
――俺は、どこに立っている?
安定している。
給与もある。
社会的信用もある。
だが、
心は、どこか乾いている。
父の暴言。
家の中の緊張。
母の沈黙。
あの頃、
「何もできなかった自分」が、
今の自分の奥に残っている。
希望の家では、
違う空気が流れている。
利用者が畑で土を触る。
笑い声が、壁に吸い込まれず外へ抜ける。
制度に縛られていないわけではない。
だが、温度が違う。
――あそこに行けば、変われるのか。
それとも、
また揺れるだけか。
4-2 副業という言葉の重さ
圭吾からメッセージが届いた。
「来月の運営推進会議、顔を出せるか?」
亮は画面を見つめたまま動けなかった。
出せる。
だが、正式な立場ではない。
緑風園では、
副業は原則申請制だ。
「何のための関与ですか?」
人事に問われれば、
どう答える。
「理念に共感しているから」では、
通らない。
亮は申請書のフォームを開く。
・業務内容
・時間
・報酬の有無
・本業への影響
報酬はほぼない。
ボランティアに近い。
だが、
本当に無報酬なのか?
心は、あの場所に引き寄せられている。
「亮、大丈夫か?」
健太から電話が来る。
「俺はもう、あっちに立つって決めた。お前はお前のやり方でいい。」
健太の声は、迷いがない。
亮は笑う。
「……兄貴は、早いな。でも俺は慎重なんだよ」
慎重。
それは強みか。
それとも逃げか。
夜、自室の天井を見つめる。
もし、希望の家が失敗したら。
融資が回らなくなったら。
事故が起きたら。
指定が更新されなかったら。
――また、家が壊れる。
その恐怖が、身体の奥に残っている。
父の影は、まだ消えていない。
4-3 守るのは、過去か未来か
ある日。
希望の家で、
利用者の女性がぽつりと言った。
「ここ、昔の家みたいで落ち着くわ」
亮はうなずく。
「よかったです」
女性は続けた。
「息子に迷惑かけたくないのよ。でも、ここなら少しだけ甘えられる」
甘える。
その言葉に、亮は胸が詰まる。
自分は、
誰かに甘えられたことがあっただろうか。
父は甘えを許さなかった。
強さだけを求めた。
だから、
自分は静かな側にいる。
波風を立てない。
感情を出さない。
だが希望の家では、
弱さが否定されない。
亮は外に出る。
冬の空は重い。
だが、遠くにわずかな光が差している。
圭吾から再びメッセージが来る。
「正式に副業申請、出した」
亮は息をのむ。
施設長は、逃げなかった。
なら自分は?
守るのは、
過去の恐怖か。
それとも、
未来の可能性か。
亮は、申請フォームに入力する。
「業務内容:地域密着型通所介護における相談支援補助」
送信ボタンを押す指が、
わずかに震える。
送信完了。
画面が静かに変わる。
揺れは消えない。
だが、立ち止まらない。
それが今の選択だった。
第5章 新潟の風
朝六時。
まだ薄暗い。
窓の外が、静かすぎる。
真奈美がカーテンを開けた瞬間、息を呑んだ。
一面の白。
音を吸い込んだような世界。
「……積もったわね」
涼太はスマートフォンで道路状況を確認する。
除雪車はまだ来ていない。
送迎開始は八時半。
間に合うか。
七時半。
車に向かうと、すでにタイヤの半分が雪に埋もれている。
スコップを手に、健太が無言で除雪を始める。
「エンジンは?」
「かかる。でも凍ってる」
ドアが重い。
冷気が肺に刺さる。
亮がチェーンを取り出す。
「念のため巻きましょう」
手袋の中で指がかじかむ。
金属が冷たい。
チェーンを装着するだけで十五分。
その十五分が、後の一時間を狂わせる。
最初の利用者宅。
坂道。
車が、ゆっくりと登る。
アクセルを踏みすぎると滑る。
弱すぎると止まる。
涼太の足の感覚が、研ぎ澄まされる。
途中で、わずかに後輪が空転した。
「……っ」
車体が横に流れる。
真奈美の心臓が跳ねる。
健太が後部座席から言う。
「大丈夫、ゆっくりで」
呼吸を整える。
少しずつ、前に進む。
何とか到着。
だが、玄関前で問題が起きる。
利用者の家の前が除雪されていない。
膝上までの雪。
「これは……」
亮が先に降りる。
雪を踏みしめながら玄関へ向かう。
利用者は八十五歳の女性。
杖歩行。
雪道は危険。
「今日は休みましょうか」
家族が言う。
その言葉は優しいが、
同時に、現実だ。
キャンセル。
一人減る。
次の家へ向かう。
二軒目。
到着直前で、対向車がスリップして停車。
道路が塞がれる。
十分。
十五分。
二十分。
利用者から電話。
「まだですか?」
声は不安だ。
涼太は謝る。
「申し訳ありません。雪で……」
受話器の向こうで、ため息が聞こえる。
信頼は、こういう日に揺らぐ。
三軒目。
坂を下る途中で、
ブレーキがわずかに滑る。
車が前に流れる。
前方に電柱。
涼太の手に汗が滲む。
ハンドルを切り、エンジンブレーキを使う。
数秒。
だが、永遠のように長い。
止まった。
誰も声を出さない。
真奈美の胸が強く打つ。
動悸。
指先が冷たい。
「……大丈夫?」
涼太が聞く。
真奈美はうなずくが、
喉が乾いている。
頭の奥で、
昔の救急車のサイレンが一瞬よぎる。
事故。
搬送。
謝罪。
やめて。
今は違う。
今は、自分が支える側。
結局、三件キャンセル。
到着が一時間以上遅れた利用者もいる。
デイルームは、いつもより静かだった。
暖房の音がやけに大きい。
「冬はこんなもんだよ」
健太が言う。
だがその声は、
どこか強がりだ。
亮はタブレットの収支表を閉じる。
三件キャンセル。
売上は三万円近く減る。
だが人件費は変わらない。
雪は、利益率まで奪っていく。
稼働率、六割。
このまま続けば赤字。
暖房費は上がる。
燃料代も。
理想は、
雪を溶かしてはくれない。
午後。
ようやく雪が弱まる。
利用者の一人が言う。
「今日は来られてよかった」
その一言に、
真奈美の肩の力が抜ける。
たった一人でも。
ここを必要とする人がいる。
縁側の外は白い世界。
冷たい風が窓を鳴らす。
新潟の冬は、甘くない。
送迎は命を預かる行為だ。
一瞬の判断ミスが事故になる。
経営は天候に左右される。
人は自然に勝てない。
それでも。
涼太は車のキーを握りしめる。
「雪が降っても、迎えに行く」
真奈美が小さく笑う。
「無理はしないで」
守るだけではなく、
続けること。
それが、
この土地で生きるということ。
新潟の風は厳しい。
だが、
この家はまだ立っている。
揺れながら。
踏ん張りながら。
そして少しずつ、
光を紡いでいる。
最終章 立ち止まった日
廃屋の前に立ったあの日。
空は低く、薄く曇っていた。
日本海からの湿った風が、庭の枯れ草をゆらす。
門柱は傾き、
郵便受けは赤く錆び、
玄関の引き戸は少し歪んでいる。
静かだった。
あまりに静かで、
自分たちの呼吸の音だけが、やけに大きく感じられた。
誰も、確信は持っていなかった。
圭吾は腕を組んだまま、何も言わない。
施設長としての責任が、無言のまま背中に乗っている。
亮はポケットに手を入れ、足元を見ている。
視線の先には、雪解け水でぬかるんだ地面。
真奈美は、玄関の扉を見つめたまま動かない。
そして涼太だけが、少し前に立っていた。
「……入ってみるか」
その声は、強くもなく、弱くもなかった。
戸を引くと、古い木の匂いがした。
湿った畳。
閉ざされた空気。
時間の止まった空間。
床が、きしむ。
天井の梁は太く、黒光りしている。
かつてここで暮らしていた家族の気配が、まだ残っているようだった。
「ここに、居場所を作る」
涼太は、ぽつりと言った。
誰に向けた言葉でもない。
自分自身に向けた宣言。
圭吾がようやく口を開く。
「簡単じゃない」
短い言葉。
そこには、
制度も、
資金も、
責任も、
すべて含まれていた。
「分かってます」
涼太は即答しなかった。
一拍置いて、うなずいた。
亮が小さく言う。
「失敗したら?」
その問いは、誰もが抱いていた。
真奈美の胸が、かすかに締めつけられる。
また崩れるのではないか。
また失うのではないか。
守るだけの人生なら、
ここで引き返す方が安全だった。
だが――
「それでも」
真奈美は、静かに言う。
「誰かが、ここで息をつけるなら」
声は震えていない。
恐れは消えていない。
それでも、前に出た。
圭吾が庭を見渡す。
草だらけの空間。
ひび割れたコンクリート。
傾いた物置。
「……まずは、片付けだな」
それは決意ではなく、
具体的な一歩だった。
亮が苦笑する。
「雑草、すごいですよ」
「じゃあ、抜くか」
涼太が軍手を取り出す。
誰も拍手しない。
誰もドラマチックな言葉を言わない。
ただ、
草を一本、抜いた。
根が深い。
なかなか抜けない。
力を入れる。
ぶちり、と音がした。
土の匂いが立ち上る。
日本海からの風が吹く。
まだ看板もない。
まだ指定も出ていない。
まだ誰も利用者はいない。
それでも、
確かに何かが始まっていた。
確信ではない。
覚悟でもない。
引き返さないという、小さな選択。
かつて痛みを知った人々が、
もう一度、支える側へと立ち上がる。
それは派手な革命ではない。
静かな、
だが確かな、
決意の始まりだった。
あとがき
廃屋の前に立ったあの日、
私たちは何も持っていませんでした。
指定も、資金も、確信もない。
あったのは、過去に傷つきながらも
もう一度「支える側に立ちたい」という思いだけでした。
けれど、本当の物語はここから始まります。
制度という壁。
数字という現実。
副業という立場。
雪の日の送迎。
そして、それぞれが抱えた過去。
希望の家は、まだ完成していません。
揺れながら、形を変えながら、
それでも立ち続けようとしている途中です。
もしあなたが、
守るだけの人生に少し疲れているなら。
もしあなたが、
もう一度誰かを支えたいと思っているなら。
この物語は、まだ続きます。
次章では、
理想が現実に試される過程を描きます。
――「希望の家ができるまで②」へ。

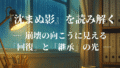
コメント ご感想や応援の言葉は、次回作へのエネルギーになります! あなたのひとことが、作品を育てます