精神科医だった父、そして崩壊した家族の物語
「沈まぬ影」という物語は、私自身の実体験に基づいているわけではありません。しかし、医療や介護の分野に関する情報に触れる中で、制度のひずみや人知れず苦しむ人々の存在を知り、次第にこのテーマに心を惹かれていきました。
現実に起きている問題を「物語」という形で描くことで、少しでも誰かの気づきや共感につながればという想いから、この作品を執筆するに至りました。
精神科医という「理想」と「現実」
物語の主人公・藤田健一は、理想を抱いて精神医療の世界に飛び込んだ医師です。しかし、彼が向き合うことになったのは、病院経営の現実、閉鎖病棟の実態、人手不足、そして「治すこと」よりも「管理すること」が優先される制度の壁でした。
本作では、精神医療や病院運営の仕組みに対して、物語としてのフィクションの中で一つの問いを投げかけています。医療従事者の視点と、患者やその家族が感じる現実とのギャップをテーマに据え、「理想と現実の狭間で揺れる人間の苦悩」を描くことが目的でした。
この設定は、報道や医療に関する文献、また社会課題として取り上げられている構造的な問題を参考にしながら構成しています。読者の皆さまにも「もし自分だったら?」と考えていただけるような視点を意識しました。
家庭の崩壊と「声なき子どもたち」
もうひとつ、この物語で描きたかったのが、「依存症が家族に与える影響」です。
健一はアルコール依存に陥り、やがて暴言や問題行動を繰り返すようになります。その背景には、治療者であるにも関わらず「患者を救えない自分」への絶望感がありました。
しかし、依存症の当事者が苦しむ一方で、見落とされがちなのが「子どもたちの心」です。健太と亮は、父の暴言に怯え、やがて心を閉ざしていきます。これは、家庭内の暴力や依存に巻き込まれた子どもたちのリアルな姿であり、「子どもは見ていないようで、すべてを見ている」ことを伝えたかった。
息子たちの視点を交えて描くことで、「父の影」は今もなお彼らの中で沈まずに残っている――というタイトルの意味が、より深く読者に届くよう工夫しました。
執筆スタイルとAIとの協働
この作品はAIとの共同作業によって構成されました。私はプロット、キャラクター、全体の構成を考えたうえで、AIとともに文章を磨いていきました。
物語の語り口を「読者の心に寄り添うようなトーン」に統一しつつ、閉鎖病棟の重苦しさ、家庭内の沈黙、そして本人が抱える罪悪感といった要素を丁寧に描写することに注力しました。
また、AIを活用することで、多様な角度からの「問い」を立てながら、読者の共感を生む構成に仕上げることができたと感じています。
SEO対策と集客への取り組み
この小説をブログで公開するにあたって、以下のキーワードを意識しました:
- 精神科医 小説
- アルコール依存 小説
- 家族崩壊 小説
- 精神病院の実態
- 医療と介護の狭間
物語中にキーワードを自然に織り交ぜるよう配慮し、読者の検索ニーズに応えつつ、重たいテーマにも「人間味」や「希望」を感じさせる構成にしました。
また、「AI小説ブログ」という特性を活かし、読みやすさ・見出しの工夫(H2、H3、要約ポイント)・読了後の導線(関連記事への内部リンクなど)にも力を入れました。
読者へのメッセージ
この作品を読んで、「自分の家族にも似た経験があった」と感じる方もいるかもしれません。あるいは、「なんでこんな重い話を書くのか」と思う方もいるかもしれません。
でも、私は「小説とは、人の心にそっと触れるものであってほしい」と願っています。
健一のような医師がいたかもしれない。
真奈美のような妻がいたかもしれない。
健太や亮のように、誰にも言えない苦しみを抱えていた子どもがいるかもしれない。
その「かもしれない」に、誰かがそっと共感できる瞬間をつくれたら――
それが、「沈まぬ影」を書いた意味です。
次回作への布石
健一の死後、物語は「紡がれる光」へとつながっていきます。
そこでは、残された家族が過去の影を抱えながら、新たな人生へと踏み出す姿を描いています。
健一の「影」は消えません。
でも、その影があるからこそ、「光」を感じることができる。
次作では、そんな再生の物語を届けたいと思っています。
読者の皆さまへ
読んでくださって、ありがとうございます。
よろしければ、コメントや感想をブログ・X(旧Twitter)でお聞かせください。
今後も、AIと共に「心を揺さぶる物語」を紡いでまいります。
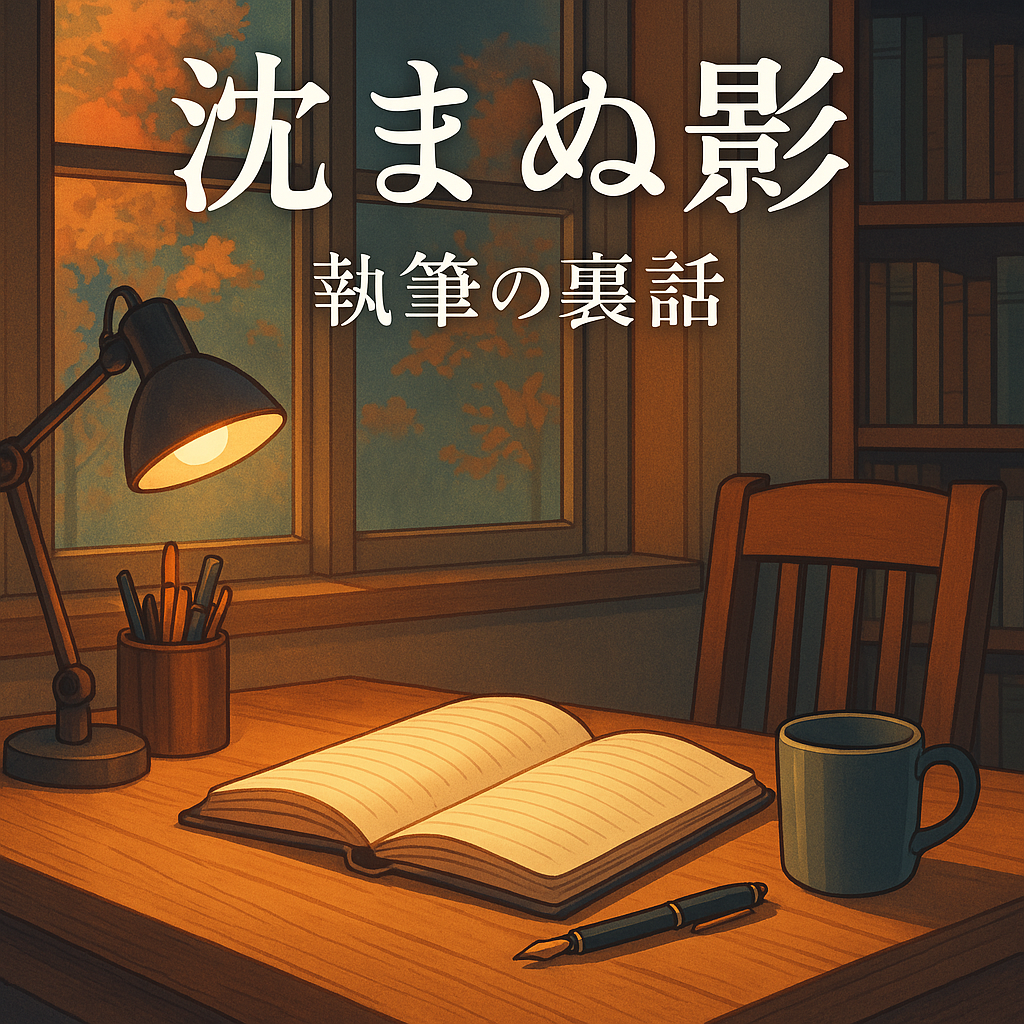
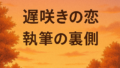
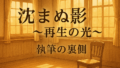
コメント ご感想や応援の言葉は、次回作へのエネルギーになります! あなたのひとことが、作品を育てます