はじめに
小説『沈まぬ影』は、精神科医・藤田健一の人生を通じて「医療と人間のはざま」を描いた物語です。理想と現実のギャップ、アルコール依存症、家庭の崩壊と再生――。これらは単なるフィクションではなく、日本の精神医療が抱えてきた構造的な課題と深くつながっています。
その背景を理解するために参考になるのが、後藤基行さんの博士論文『日本における精神病床入院の研究 ― 3類型の制度形成と財政的変遷』(2015年)です。本記事では、この論文を手がかりに『沈まぬ影』を読み解いていきます。
後藤論文が明らかにしたこと
後藤氏は、日本の精神病床入院を「3つの類型」で整理しました。
-
行政収容型(社会防衛型)
措置入院など、行政権限による強制的な収容。社会秩序の維持を優先。 -
救貧・公的扶助型(社会福祉型)
生活保護や医療扶助による入院。経済的困窮を背景に「収容の場」として病院が機能。 -
私費・社会保険型(治療型)
家族負担や保険での入院。治療目的は明確だが、必ずしも治療だけで終わらない場合が多い。
戦後日本では、このうち 「救貧・公的扶助型」 が精神病床の拡大を強力に後押ししました。病院は「治療の場」であると同時に、「生存の場」「収容の場」としての性格を持ち続けてきたのです。
さらに、患者の入院に家族が同意し、結果的に「病院に押し出す」役割を果たしてきたことも長期入院の大きな要因でした。
『沈まぬ影』に描かれる制度の影
小説『沈まぬ影』には、こうした制度の影響が随所に描かれています。
-
理想と現実の狭間に立つ医師
健一は「患者を社会復帰へ導きたい」という理想を持ちながら、病院経営の借金・人手不足・病床利用率維持といった制約に押しつぶされます。これは「治療型」よりも「収容・扶助型」が色濃い現場のリアリティと重なります。 -
家族の苦悩と斥力
妻・真奈美や子どもたちは、健一の依存と暴言に苦しみ、やがて家庭が崩壊します。ここには「患者を病院に押し出す」家族の役割と負担が象徴的に表れています。 -
閉鎖病棟と「帰りたい」の声
患者・田村の「もう元気になった、出してほしい」という訴えは、制度的に退院が困難な現実を突きつけます。後藤論文が指摘する「長期在院」の問題と響き合う場面です。
小説と論文が交差する地点
後藤論文と『沈まぬ影』を重ねて読むと、次のような問いが浮かび上がります。
-
医療は治療か、それとも収容か?
健一が投げかける「これは本当に医療なのか?」という問いは、戦後日本の精神医療そのものが抱えてきた矛盾を凝縮しています。 -
家族に背負わせてきたものは何か?
扶助制度や同意入院は、患者を守ると同時に、家族に大きな負担と葛藤を与えてきました。真奈美や子どもたちの姿は、その縮図です。 -
再生の可能性はどこにあるのか?
物語の終盤に描かれる「赦しと対話」は、個人の努力だけでなく、リハビリや地域医療、社会保障制度の支えがあって初めて成立する希望だと読み取れます。
結びに ― 「沈まぬ影」を社会へ返す
『沈まぬ影』は、精神科医の崩壊と家族の痛みを描きながら、その背景にある日本の精神医療制度の矛盾を浮かび上がらせています。
後藤論文が示す「3類型の入院構造」と「家族・制度の役割」を踏まえて読むことで、物語は単なるフィクションを超え、現実社会への問いかけとして響いてきます。
制度に支えられ、制度に縛られ、時に制度に押しつぶされる人間たち――。
その姿を描くことこそが、『沈まぬ影』という作品の核心なのではないでしょうか。
参考文献
-
後藤基行『日本における精神病床入院の研究 ― 3類型の制度形成と財政的変遷』一橋大学博士論文, 2015年.
一橋大学機関リポジトリ HERMES
関連記事

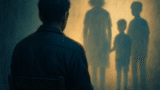
コメント・ご感想をぜひ!
あなたは「これは本当に医療なのか?」という問いにどう答えますか?
ぜひコメント欄で、感じたことや考えを共有してください。
あなたのひとことが、次の作品を育てる力になります。
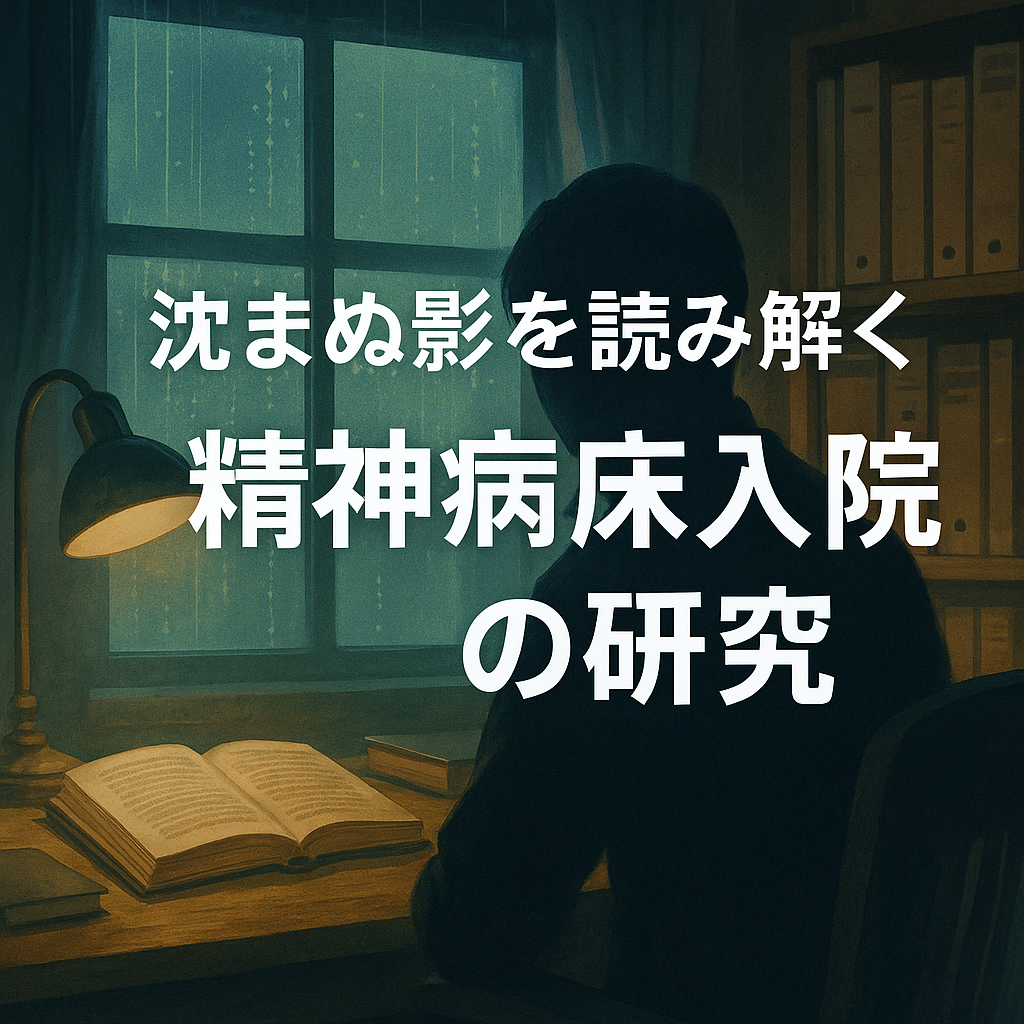
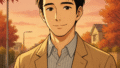
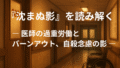
コメント ご感想や応援の言葉は、次回作へのエネルギーになります! あなたのひとことが、作品を育てます