あらすじ
IT企業に勤め、順調なキャリアを歩んできた山田涼太(35歳)。
しかし心のどこかに満たされぬ違和感を抱えながら日々を過ごしていた。
ある日、久しぶりに母を訪ねた帰り道、偶然目にした「在宅介護」に関する市民講演会のポスター。
祖母の最期を思い出し、心に去来する後悔と向き合うように、彼はその講演会へと足を運ぶ。
そこで登壇していたのが、医療事務として働く藤田真奈美(50代)。
夫の介護を経験し、医療現場でも家族の痛みに寄り添ってきた女性だった。
その言葉は、涼太の胸に静かに、しかし深く響いた。
後日、偶然の再会を果たしたふたり。
年齢も立場も違うが、互いに心の奥に抱える「喪失」と「再生」の記憶が共鳴し、
やがて少しずつ距離を縮めていく。
一方、真奈美は亡き夫の影、母としての責任、年齢への引け目に揺れながらも、
涼太のまっすぐな言葉と優しさに、心が少しずつほどけていく。
涼太もまた、祖母との記憶、母への想い、そして新しい人生への一歩として、介護の道を志し始める。
――これは、人生の折り返しを迎えた一人の女性と、
過去の後悔と未来への希望を抱いた年下の男性が出会い、
ゆっくりと愛と信頼を育んでいく、遅咲きの恋物語。
たとえ傷ついた過去があっても。
たとえ不安な未来があっても。
人は、もう一度誰かを愛し、信じることができる――
そう信じさせてくれる、やさしく温かな再生の物語。
第1章:静かな違和感
朝の通勤電車は、いつも通りの混雑だった。
淡々とスマホをスクロールしながら、涼太は吊革につかまっていた。スーツ姿のサラリーマンたちの無言の波に紛れて、彼もまた、感情を殺した一人として揺られている。
IT系企業に勤めて十年あまり。
仕事は順調だった。成果も上げているし、職場の人間関係も悪くない。上司からの信頼も厚く、次期プロジェクトリーダーの話もある。
けれど――
心の奥底に沈んでいる、言葉にならない「何か」が、時折、涼太を締めつけた。
「……なんでだろうな」
誰にともなくつぶやいた言葉は、電車の軋み音にかき消された。
週末、母のもとを久しぶりに訪ねた。
築三十年の一軒家。祖母が亡くなった後も母はひとりでこの家に住み続けていた。
「何か食べていくでしょ?」
母の笑顔は変わらなかったが、その手のしわは増えていた。ふと台所に立つその後ろ姿が、祖母に重なって見えた。
「……ばあちゃん、よくここにいたな」
ついこぼれた言葉に、母は少し手を止めて笑った。
「そうね。あの頃は毎日が戦争だったわ。夜中でも起きるし、おむつも、食事も……。でもね、あの人、最期まで自分で食べようとしてたのよ。えらかったわ」
涼太は返す言葉を失った。
あの頃、自分は何をしていただろう。会社にかまけて、家にはあまり帰らなかった。介護の現実から目を逸らしていた自分がいた。
「……もっと、できたことあったよな」
「……え?」
「いや、なんでもない」
あのときの無力感が、ふいに胸に蘇る。
祖母が亡くなった夜、母が泣いていたこと。自分は声もかけられず、ただ背中を見ていたこと。
心に小さく沈んでいた何かが、またひとつ形を持ち始めていた。
帰り道、涼太はふと立ち寄ったカフェの壁に貼られたポスターに目を止めた。
「在宅介護のこれから――家族が支え合う社会を目指して」
市民向け講演会/今週土曜 午後2時~/市民福祉会館にて
白い文字が、やけにまぶしく見えた。
――家族が支え合う、か。
あの時、自分がもう少し違う選択をしていたら、母も祖母も、もう少し違う時間を過ごせたんだろうか。
「……行ってみるか」
誰に誘われたわけでもないのに、そう呟いた自分が不思議だった。
ただ、心のどこかで、「今度はちゃんと向き合いたい」と思った。
まだそれが何に繋がるのか、わからないまま――。
第2章:講演会と出会い
講演会当日。
土曜の午後、市民福祉会館の小ホールには、年配者から若い世代まで、思いのほか多くの人が集まっていた。
受付でパンフレットを受け取った涼太は、最後列の静かな席に腰を下ろした。
壇上には「在宅介護のこれから――家族が支え合う社会を目指して」と大きな垂れ幕が掲げられている。
(こんなに人、来るんだな)
軽い驚きとともに、どこか心強さもあった。
自分だけじゃない。誰かを支えたいと、何かを変えたいと思っている人が、ここにはいる――そんな空気を感じた。
最初に登壇したのは、地元のケアマネジャーだった。
在宅介護における現実、制度の壁、支援の限界。
どれも耳が痛いほどリアルで、涼太は気づけば真剣にメモを取っていた。
そして最後に、登壇者の一人として紹介された女性がいた。
「医療事務として在宅支援に関わってこられた、藤田真奈美さんです」とアナウンスされる。
壇上に現れたその女性は、控えめな仕草と落ち着いた表情で、ゆっくりとマイクの前に立った。
50代だろうか。やわらかな黒髪をまとめ、シンプルなワンピースに身を包んだその姿は、どこか知的で凛としていた。
「私は専門家ではありません。ただ、かつて家族を介護し、その後も医療の現場に身を置いてきた一人として、今日お話させていただきます」
その声には、不思議な温かさと静かな力があった。
真奈美の語る経験は、派手さはなかった。
だが、そこには「生きた言葉」があった。
「……私は、夫の変化にずっと気づいていたのに、どうすればよかったのか、今も正解はわかりません。でも……誰かに頼っていいんだって、もっと早く気づいていたら、違っていたかもしれない」
涼太は、息をのんでいた。
(……頼ってよかったのかもしれない)
その言葉が、自分の過去を切り取ったように思えた。
祖母の介護、母の沈黙、そして見て見ぬふりをした自分。
彼女の話は、まるで許しのようだった。
過去を責めるでもなく、誇るでもなく、ただ「生きた証」として語る彼女の姿が、心に深く刺さった。
講演会の終了後、ふと視線を感じて振り返ると、彼女――真奈美が出口近くで参加者に会釈をしていた。
ふと、目が合った。
一瞬だけだった。けれど、その瞳は確かにこちらを見て、微かに、笑ったように思えた。
涼太の胸の奥で、何かが小さく震えた。
初めて会ったはずなのに、どこか懐かしさに似た感情が湧いた。
「……あの人、誰かに似てる」
そう呟いて、自分でも気づく。
それは、祖母でも、母でもない。
かつて何かを失い、それでも誰かを支えようとする――そんな「人の強さ」そのものだった。
講演会の帰り道、秋の風が心地よく吹いていた。
その風のなかに、ふと花の香りが混じったような気がして、涼太は少しだけ笑った。
まだ名前すら知らない人のことを、もう一度会いたいと思った。
そんな感情が、自分の中に芽生えていることを、確かに感じていた。
第3章:再会と揺れる心
介護職の資格取得を目指し、平日は仕事をこなしながら土日は講座や施設見学に足を運ぶ日々。
だが、あの講演会の日だけは、何かが違っていた。
涼太の中に、ひとりの登壇者の姿が、いまだ焼きついて離れなかった。
「家族の介護は、いつも正解のない選択の連続でした。
でも私は――それでも、母として、妻として、できることをしたかったんです」
壇上でそう語った女性。
決して大きな声ではなかったが、その言葉には重みと、にじむような悲しみ、そして温もりがあった。
名前は……確か、「藤田真奈美」。
涼太は、その名前をネットで検索しようとした手を止めた。
なぜか、知りすぎてはいけない気がしたのだ。
ある平日の夕方。
涼太は講演会で名刺交換した地域包括支援センターの職員に勧められ、ある医療法人が運営する在宅支援チームのオリエンテーション見学に出向いた。
案内を受けて資料室に向かう途中、事務室のカウンターにふと目を向けると、そこに――
「……あ」
書類を綴じていた女性が顔を上げた。
その瞬間、お互いの目が合った。
藤田真奈美――あのとき、壇上に立っていた人だった。
「……講演、聞かせていただきました。すごく……心に響きました」
「……ありがとうございます。あの日は、実はすごく緊張していて……ちゃんと届いていたか、わからなかったんです」
「とても、届きました。言葉のひとつひとつが、まっすぐでした」
一瞬の沈黙。
だがその沈黙は、気まずさではなく、なにかを確かめるような間だった。
涼太は、自分の鼓動がいつもより早いことに気づいていた。
介護の勉強を始めてから、いろんな専門家の話を聞いてきた。
だが――こんなふうに、話したいと思った人は初めてだった。
彼女の言葉は、彼女の表情は、自分の中の「何か」を静かに揺らした。
一方で、真奈美もまた心の波を感じていた。
(この人……なぜこんなに真っ直ぐな目をするのだろう)
いつしか忘れていた感情。
人とまっすぐ目を合わせて話すことの、怖さと懐かしさ。
彼女はそっと口角を上げると、「また、どこかで」とだけ言って軽く頭を下げた。
涼太も、自然に頭を下げた。
二人のあいだに、言葉以上の何かが、確かにあった。
――偶然、なのだろうか。
でも、あの日、あの声を聞いたときから、もう何かが始まっていた気がする。
涼太は、胸の内でその言葉を繰り返していた。
第4章:踏み出せない想い
再会から数日後。
涼太のデスクの引き出しには、折りたたんだ小さな紙切れがしまわれていた。
そこには、「何かあればこちらへご連絡くださいね」と言って、真奈美が差し出してくれた名刺と、彼女の手書きの携帯番号。
涼太は、そのメモを何度も開いては閉じた。
連絡を取る理由は、ある。
「介護の勉強について聞きたいことがある」
「講演会で言っていたことをもう少し知りたい」
けれど、なぜか指は動かない。
(本当に勉強が理由なんだろうか……)
自分の中にある感情が、ただの敬意ではないことに、涼太は気づき始めていた。
一方、真奈美もまた、心を落ち着かせられずにいた。
あの日の若い男性――山田涼太。
丁寧な口調、まっすぐな視線、そして、あの別れ際のささやかな笑顔。
(まさか……惹かれてなんて、いないよね?)
心のどこかが騒いでいる。
けれど、その感情に名前をつけることに、強い抵抗があった。
彼女の中には、「自分はもう恋なんてする年齢ではない」「家族を支えることで精一杯」という長年の思い込みが根を張っていた。
そして――夫・健一のことも。
アルコール依存に苦しみ、家族を巻き込み、静かに逝っていったあの人の記憶は、今も真奈美の心に影を落としていた。
週末、涼太は郊外の墓地を訪れた。
風の強い丘の上、小さな墓石の前にしゃがみ、線香を手向ける。
「ばあちゃん……元気にしてるか? いや、そっちは静かだよな」
在宅で最期まで看取った、あの数ヶ月。
苦しかったけれど、逃げなかった時間。
今思えば――あれが、自分の原点だった気がする。
(もっとできることがあったんじゃないか)
そんな悔いを、ずっと引きずってきた。
けれど、祖母が最期に見せた笑顔を思い出すたび、涼太の胸は不思議とあたたかくなった。
「介護は、支えるだけじゃなく、つながることでもあるんです」
あの日、真奈美が講演で語った言葉が脳裏をよぎる。
涼太は、ゆっくりと手を合わせた。
(俺は、もう一度……誰かと、つながりたいのかもしれない)
その夜、涼太はスマートフォンを手に取った。
あのメモの番号を画面に打ち込み、入力された数字をしばらく見つめる。
「こんばんは。山田涼太です。
先日はありがとうございました。
もしご迷惑でなければ、また少しだけお話を伺えたら嬉しいです。」
そう打って、数分悩み……送信ボタンを押した。
胸が高鳴っていた。
(これが恋なのかどうかは、まだわからない。でも――)
知りたいと思った気持ちは、本物だった。
その頃、真奈美は帰宅後に家事を終え、リビングで一息ついていた。
スマートフォンに通知が入り、見慣れない名前が表示された。
「山田涼太さん……?」
彼女の指が、自然にメッセージを開いた。
そして、ゆっくりと微笑んだ。
(まさか、本当に連絡をくれるなんて)
心のどこかで、少しだけ――ずっと、待っていたのかもしれない。
夜の空は静かに晴れていた。
それぞれの部屋で、それぞれの心が、少しだけ前に進もうとしていた。
――もう一度、人を信じてみること。
それは思ったより、怖くて、でもあたたかい。
第5章:心が揺れる夜
その夜、涼太は眠れなかった。
スマートフォンに表示された通話履歴を何度も見返しながら、窓の外を眺めていた。
「また、お会いできますか?」
「ええ。私も、話せてよかったですから」
真奈美の柔らかな返事が、耳に残っていた。
あの短い一言が、なぜこんなにも胸を熱くするのだろう。
ふと、祖母の手を握っていた最期の夜を思い出す。
痩せた手のぬくもり。
「ありがとう」と微笑んだ顔。
(あのとき俺は、無力だった。だけど――)
誰かを守りたいと願ったあの夜が、今の自分に繋がっている。
そして真奈美の、
「もっと早く気づいてあげられたらって、今も思います」
という言葉が、心の奥深くに残っていた。
彼女もまた、誰かを守ろうとした人だった。
一方、真奈美もまた眠れずにいた。
風呂上がり、タオルで髪を乾かしながら、自分の頬がほんのり紅くなっているのに気づく。
(なにをやってるの、私……)
彼は誠実で、まっすぐで、傷ついた誰かに寄り添える人だった。
でも自分は――。
(もう若くもない。家族を背負って、夫も看取って……)
心の奥底に「こんな私に、もう誰かを惹きつける価値なんてあるのか」という思いがちらつく。
それでも、涼太の瞳はあの日、真っ直ぐに自分を見ていた。
朝、メールが届いていた。
「昨日はありがとうございました。もしご都合よければ、今度はもう少しゆっくり、お食事でもしませんか?」
一行だけの短い文に、どこか彼の不器用な誠実さがにじんでいる。
真奈美はしばらく指先を止めていたが、やがて返事を打った。
「こちらこそ、ありがとうございました。……ぜひ、行きましょう」
送信ボタンを押した瞬間、
自分の中で何かが動いた気がした。
――揺らぎながらも、人はまた誰かを信じようとする。
たとえ、過去に傷ついた経験があっても。
この気持ちは、きっと後戻りできない。
でも、それでも――もう一度、歩いてみたいと思った。
第6章:揺らぎと確信
その日、涼太はやけに早く目が覚めた。
眠れなかったわけではない。ただ、目が覚めてからというもの、胸の高鳴りが収まらなかった。
(今日、ちゃんと伝えよう)
その「ちゃんと」が、何を意味するのか、自分でもまだ少し曖昧だった。
でも、たしかに言えるのは――
「彼女と過ごす時間が、今の自分にとってかけがえのないものになりつつある」ということだった。
待ち合わせ場所に早く着きすぎた涼太は、スマートフォンをいじるふりをして、何度も入口に視線をやる。
そしてふと、ふわりとしたベージュのコート姿が視界に入った。
(……来た)
いつもより少しラフな装いの真奈美は、控えめな笑顔で小さく会釈をした。
その仕草が、なんとも言えず可愛らしかった。
コーヒーの湯気の向こうで、真奈美はゆっくりと語る。
健一のこと、家族のこと、自分の過去のこと――。
「……でも、そんな私でも、誰かとちゃんと向き合えたらって、少しだけ思えるようになったんです」
そう語る彼女の横顔を見ながら、涼太は思った。
(こんなふうに誰かの人生を、ちゃんと聞きたいと思ったのは初めてだ)
それは同情ではなく、共感でもなく、
「これからもそばにいたい」という、願いのようなものだった。
だが、心のどこかで、ためらいもあった。
年齢のこと。立場のこと。過去のこと。
(こんな俺が、彼女の人生に入り込んでいいのか?)
けれど、真奈美がふと笑ったとき、その不安は静かに溶けていった。
「……山田さんは、どうしてあの講演会に?」
と聞かれ、涼太は祖母のことを話した。
最期まで在宅で介護をしたこと、母と共に支えた時間がどれほど大切だったか。
そして、
「……今も、できることがあればって思ってます。仕事でも、人生でも」
と、言葉を継いだとき――
真奈美は、少し驚いたように目を見開いていた。
「……すてきな方ですね」
その言葉に、胸の奥が熱くなった。
カフェの席に流れる静かな空気の中で、
真奈美がふと視線を落としたその一瞬――
涼太は、意を決して言葉をこぼした。
「……俺、真奈美さんのことが、好きです」
それは決して軽い気持ちではなかった。
この想いを伝えるために、今日ここへ来たのだと、ようやく自分でも気づいた。
彼女がどんな反応を返すかはわからない。
でも、「言うこと」だけは、決めていた。
――どれだけ過去に傷があっても。
どれだけ未来が見えなくても。
それでも「今、この人のそばにいたい」と思えた気持ちは、嘘じゃない。
これは始まりの一歩。
そして、揺らぎの中でようやく見つけた、確かな想いだった。
第7章:未来を描く場所
カフェを出て、二人は駅までゆっくりと歩いた。
12月の空気は澄んでいて、夕暮れの光が街を柔らかく染めていた。
さっきの告白に対して、真奈美は何もはっきりした返事をしていない。
でも、それが不思議と苦ではなかった。
(今日という一日が、何かを動かした気がする)
それだけで、十分だった。
帰りの電車に揺られながら、涼太は車窓の向こうに目をやった。
遠くに、夕焼けに染まる団地の屋根が見える。
(誰かの日常って、こんなふうに無数に広がってるんだ)
あの講演会に行こうと決めた日。
祖母の介護をしていた日々が、ふいに思い出された。
買い物の途中で転倒し、しばらく寝たきりになった祖母。
仕事をしながら支える母と、自分。
病院からの退院を在宅という選択にして、何度も不安にかられたこと。
それでも、笑っていた祖母の顔。
「最期がどこで、誰と、どう過ごせるかって、大事だと思うんです」
あのとき、登壇した真奈美がそう語った。
その言葉が、涼太の心に強く残っていた。
彼女は、自分の経験を通して、「在宅介護」の可能性を信じていた。
それは、「悲しみを越えてきた人の言葉」だった。
(こんなふうに、人を支える仕事ができたら――)
ぼんやりと、でも確かな光が見えた気がした。
今の仕事を続けていても、不満はなかった。
営業の職場には仲間もいて、それなりに成果も出していた。
でも、どこかで思っていた。
(このままでいいのか?)
誰かの役に立ちたいという気持ちが、形にならないまま積もっていく。
そしてそれが、今日、真奈美と出会い、言葉を交わしたことで、少しだけ輪郭を持ちはじめた。
家に帰ると、久しぶりに母とゆっくり話した。
祖母のこと。講演会のこと。そして真奈美のこと。
母は驚いたように笑いながらも、優しく言った。
「あんたらしいね。だけど、あんたがほんとに思ってることなら、応援するよ」
その一言が、背中を押してくれた。
数日後、涼太は地域の福祉支援センターを訪れた。
介護業界について調べ始め、資格取得のこと、制度のこと、少しずつノートにまとめていった。
「いつか、自分の手で、誰かの居場所をつくりたい」
それは漠然とした夢だった。
けれど、それを「夢」として語れるようになったこと自体が、変化の証だった。
そして、その原点には――
あの日、真奈美が語った言葉と、静かに見せてくれた「再生の強さ」があった。
――過去の痛みが、未来の光になる。
誰かと出会い、心が動いたその瞬間から、人は変われるのかもしれない。
まだ何も形にはなっていない。
けれど確かに、心の奥に「未来を描く場所」が生まれていた。
最終章:遅咲きの花
春が来た。
桜の花が、風に乗って舞い落ちる。
真奈美と出会った冬の講演会から、数ヶ月。
涼太の中で、確かに何かが変わっていた。
福祉の勉強を始め、介護現場を見学し、資格取得のための講座にも通い始めた。
最初は戸惑いもあったが、今は心から思える。
「この道を、選んでよかった」
この数ヶ月、真奈美とは何度も会った。
何気ない会話、食事、散歩。
恋人とも、まだ言えないような、けれど確かに近づいていく関係。
ある日の夕暮れ、真奈美の家の近くの公園で、涼太はふと立ち止まった。
街灯の明かりが、柔らかく足元を照らしていた。
「あの日……カフェで言ったこと、まだ覚えてますか?」
真奈美は静かに笑ってうなずいた。
「……覚えてるわよ。あのときのあなたの顔、ずっと忘れられなかった」
夜の風がそっと吹き抜けた。
彼女の髪が揺れ、街灯の下でふと見せた微笑みが、涼太の胸に深く刻まれる。
「今も、変わってません。
ずっと、真奈美さんのそばにいたいと思ってるんです」
沈黙が、数秒だけ流れた。
けれどそれは、拒絶の気配ではなかった。
真奈美はゆっくりと、まっすぐ涼太を見て、言った。
「……怖いのよ。
こんな年齢で、また恋をしていいのか、母親としてこれでいいのか。
でもね――涼太さんといると、不思議と未来のことを考えられるの」
その一言に、涼太の胸がじんと熱くなった。
帰り道、二人は並んで歩きながら、静かな夜風を感じていた。
街灯の向こう、ふと視界に入ったのは、一本の桜の木。
周囲の木々がすでに葉桜になっている中、その木だけが満開の花を咲かせていた。
真奈美が足を止める。
「……遅咲きね、この木」
ぽつりと漏らしたその言葉に、涼太も立ち止まり、花を見上げた。
「……遅くても、ちゃんと咲けたなら、それでいいんじゃないかなって……」
そう言いながら、少し照れたように視線を逸らす。
「……俺たちも、そういう花なんじゃないかって思ったんです」
真奈美は驚いたように涼太を見つめたあと、そっと微笑んだ。
その笑顔は、どこかあたたかくて、過去の痛みさえもやさしく包み込むようだった。
「ありがとう、涼太さん……」
そして、自然に、彼女の手が涼太の手に触れた。
涼太もゆっくりとその手を握り返す。
言葉にしなくても、もう伝わっていた。
たとえゆっくりでも、迷いながらでも、二人はここまで歩いてきたのだ。
もう、誰の代わりでもない。
過去の痛みに引きずられるだけの自分たちではない。
これからは――二人で、一緒に。
夜風が、満開の桜の花びらをやさしく揺らしていた。
――咲く時を待っていた花は、遅かったかもしれない。
けれどその分だけ、風にも、雨にも、やさしい強さを知っていた。
「この人生でよかった」と言える未来へ、今、歩き出している。
あとがき
『遅咲きの恋 ―涼太の章―』を最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この物語は、本編『遅咲きの恋』で描ききれなかった、山田涼太という一人の男性の心の旅路を、彼自身の視点から辿ったスピンオフです。
誰かを「想う」という感情は、時に、過去の痛みや、自分自身の未熟さと向き合うことを強いるものです。
涼太という人物は、ただ優しいだけの青年ではなく、葛藤や迷い、そして後悔を抱えながら、
一歩ずつ「人としての強さ」を獲得していった人物です。
――祖母の介護をめぐる後悔。
――母への思慕と償いの気持ち。
――真奈美という女性に出会い、惹かれながらもためらう心。
彼の成長には、誰かを「支えたい」「理解したい」と願うまっすぐな想いがありました。
けれどそれは、相手のすべてを受け入れるという覚悟と、自分の人生を変えるという決意が必要なものでもあります。
この章を書きながら、私は「若さとは何か」という問いに向き合い続けました。
それは未熟さや情熱ではなく、失敗してもまた立ち上がる力、信じたいと願う強さではないかと感じています。
そしてもう一つ。
年齢や立場を越えて、人は惹かれ合い、互いに影響し合うことができる――
そんな希望を、この物語に込めました。
真奈美という存在に出会い、変わっていく涼太の姿を、
読者の皆さんが自分自身の経験や感情と重ねながら読んでくださったなら、これ以上の喜びはありません。
涼太の物語は、彼と真奈美が共に歩む人生の一部にすぎません。
けれど、彼が何を大切にし、どんな想いで彼女に手を差し伸べたのか――
その背景を丁寧に綴ることで、本編とはまた違った「遅咲きの恋」の輪郭が見えてきたように思います。
人生には、早咲きの花もあれば、遅咲きの花もある。
けれど、大切なのは「咲く」という意志を持ち続けること。
涼太は、その意志を胸に、静かに歩き出しました。
これからも、彼のように、自分の人生とまっすぐに向き合う登場人物たちを描いていきたいと思います。
改めて、この作品を手に取ってくださったあなたに、心からの感謝を込めて。
――著者より

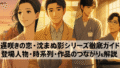
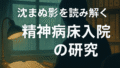
コメント ご感想や応援の言葉は、次回作へのエネルギーになります! あなたのひとことが、作品を育てます