あらすじ
夫の死から十年以上。50代の医療事務員・藤田真奈美は、母として、社会人として、ただ「日々をこなすだけ」の生活を送っていた。
夫のアルコール依存と暴言によって崩壊した家庭、そして息子たちを守るために閉ざしてきた「女としての自分」。
そんな真奈美の前に現れたのは、30代半ばの誠実な会社員・山田涼太。
偶然の出会いから始まった小さな会話。重ねた時間の中で、彼女の心にわずかに灯る希望という名の光。
「こんな歳になって、もう恋なんて……」
そう思っていた真奈美が、再び「人を愛する」という感情と向き合いながら、自分自身を取り戻していく――。
これは、過去と向き合いながらも、未来へ歩き出す遅咲きの恋の物語。
登場人物紹介
藤田 真奈美(ふじた まなみ)
年齢:50代後半
職業:医療事務
性格:強く、優しく、でも不器用。人のために尽くす反面、自分の幸せを後回しにしてしまう一面も。
背景:夫・健一の死後、子育てに専念し、恋愛を避けて生きてきた。年齢や外見に対するコンプレックスがあり、「女」としての自分を封印していた。
山田 涼太(やまだ りょうた)
年齢:30代半ば
職業:元会社員 → 介護施設職員を志す
性格:誠実で穏やか、相手の気持ちに寄り添う力を持つ
背景:仕事にやりがいを感じられず、人生を見つめ直していた時期に真奈美と出会う。彼女への想いを胸に、介護の世界へ飛び込む決意をする。
藤田 健太・藤田 亮
年齢:ともに20代後半〜半ばの息子たち
背景:健太は母を守りたい気持ちが強く、真奈美の恋に警戒心を持つ。一方の亮は、新しい家族の形に少しずつ理解を示していく。
第1章:もう恋なんてしないと思っていた
春の終わり。
藤田真奈美は、病院の医療事務室で無言のままモニターを見つめていた。受付カウンター越しに、季節の花が咲く庭が見える。その風景がどんなに鮮やかであっても、今の彼女の心には色がなかった。
──きれいね。
かつてなら、隣の同僚とそんな言葉を交わしたかもしれない。
でも今は、何も感じないふりをすることで、かろうじて自分を保っている日々だった。
夫・健一の死から10年。
誰にも言えない孤独と、言葉にできない喪失の重さを抱えて、ただ生きていた。
いや、正確には「耐えていた」のかもしれない。
女としての自分も、誰かに甘えることも、すべて封じ込めて。
──もう恋なんてしない。
そう決めていたし、もう二度と、心が揺れることはないと思っていた。
そんなある日、地域の福祉講演会のポスターが目に留まった。
「在宅介護のこれから――家族が支え合う社会を目指して」
一瞬、目を逸らしかけたが、「家族」という言葉に胸がチクリと痛んだ。
(行ってみようかしら)
それは、ほんの気まぐれだった。
第2章:心の隙間に入り込んだ光
講演会の日、真奈美は普段より少しだけ丁寧に化粧をした。
久しぶりの外出。会場の空気は、春の花粉と新生活の匂いで満ちていた。だが、彼女の心は重く、少し緊張していた。
(こんなところに来ても、誰かと話すわけじゃない。話す必要なんてない)
手にしたパンフレットには、「在宅介護のこれから」と書かれていた。心に触れるような言葉ではなかったが、それでも足を運んだのは、子育てが一段落し、空白の時間がふと心を締めつけてきたからかもしれない。
講演が始まり、壇上に立った若い男性の声が響いた。
「はじめまして。会社員として働いてきましたが、ある日ふと、自分が誰のために働いているのか分からなくなったんです」
その声に、真奈美は思わず顔を上げた。
彼の目は、まっすぐだった。誰かに見せるための表情ではなく、自分の内側を語るような静かな眼差し。
(この人……誰かに似ている)
夫の健一ではない。
むしろ、健一にはなかった弱さと誠実さがあった。
彼の語る言葉は、どれも飾り気がなく、だからこそ、彼女の奥深くにある何かが少しずつほぐれていくようだった。
「家族の介護を通して、人生の意味を考え直すようになりました。誰かを支えることが、自分を支えることにもなる。今は、介護の道へ進む準備をしています」
その言葉に、真奈美の喉の奥がぎゅっと締め付けられた。
(誰かを支えることで、自分が支えられる……?)
かつての自分がそうだった。
子どもたちの笑顔に救われながら、夜ごと健一の怒声に耐えた日々。
明け方に泣いている息子たちの寝顔に、心をつないでもらった。
自分を誰が救ったかと問われれば――答えは、「誰もいない」。
だからこそ、彼の言葉は刺さったのだ。
講演が終わる頃には、彼の名前だけが頭に残っていた。
「山田涼太」。
平凡な名前。でも、彼の語った言葉と、その誠実な空気感は、心のどこかに確かに刻まれていた。
講演会が終わった後も、真奈美は席を立てずにいた。
周囲が次々と立ち上がり、あちこちで名刺交換や挨拶が交わされる中、彼女だけがポツンと椅子に腰を沈めていた。心の中にざわざわと広がっていくものが、なにかを問いかけていた。
「――あなたの言葉が、心に残りました」
そう声をかけてきたのが、山田涼太だった。
あのときの彼は、まだどこかぎこちなく、うまく目を合わせることができないような様子だったのに、言葉だけは真っ直ぐだった。
「え……?」
驚いたように返した真奈美の声は、小さく震えていた。
「誰かの人生にそっと寄り添える仕事がしたいって、お話されてましたよね。……僕、その言葉に救われた気がしたんです」
講演中、真奈美は自分が話したことすら忘れかけていた。ただ、用意された原稿を読むだけで精一杯だったのに――誰かに届いていた。
(この人は、本当に……聞いてくれていたんだ)
胸の奥が、じんわりと温かくなっていく。何年ぶりだろう。誰かに、正面から「あなたの言葉に救われた」と言われたのは。
「そんな……立派なことを言えるような人間じゃないんです。私は……ただ、病院の事務員で」
そう返した自分の声に、どこか負い目のようなものが滲んでいた。
私はただの脇役なんです――そう言い聞かせることで、これまで自分の役割を納得させてきた。
でも涼太は、少し困ったように笑って言った。
「……”ただの”なんて、言わないでください。僕にとっては、その“ただの”一言が、前に進むきっかけだったんです」
その言葉に、真奈美は息を呑んだ。
涼太の声は静かだったが、迷いのない光があった。まるで、自分の中の奥深くにしまい込んでいた女性としての自己肯定感にそっと触れられたような感覚だった。
(この人……私を、ちゃんと見てくれてる)
息子たちからも、同僚たちからも、いつしかお母さんや職員さんという役割の中でしか見られなくなっていた自分。夫の暴言に怯えながら、家族を守るために必死で自分を殺してきた年月。
それでも――誰かの心に何かを残すことができたとしたら。
(……私にも、まだそんな力が残っているの?)
その夜、自宅に戻った真奈美は、自分でも驚くほどぼんやりしていた。
台所に立ち、湯を沸かしながら思い出すのは、涼太のあの目――真っすぐで、でもどこか迷いを抱えたままの青年のまなざし。
「あの子……どうして、あんなふうに話せるのかしら」
呟いた自分の声に、少しだけ熱がこもっていたことに気づき、慌てて湯気に紛らせた。
(何を期待してるの……私)
彼には彼の人生がある。若くて、前向きで、これからたくさんの人と出会っていくであろう彼。
(私なんかが、あの子に何かを思っても仕方ない)
そう自分を叱るように、深く息を吐いた。
けれど、心のどこかで何かが目覚めていた。まるで、長い冬を越えてふと差し込んだ春の陽射しのように。閉じていたはずの感情の蕾が、微かに膨らみ始めていた――
第3章:再会と揺れる心
あの日の講演会から数日後、真奈美はいつものように職場の医療事務室で仕事に追われていた。朝の受付対応、保険請求、カルテの整理。長年の習慣で手は動くのに、心はどこか空白を抱えていた。
(なんだか……落ち着かない)
胸の奥に残る、あの柔らかな声と視線。山田涼太――あの穏やかな眼差しが、ふとした瞬間に思い出される。心を見透かされたような、不思議な感覚。自分でも理由がわからないまま、彼の存在が離れなかった。
そんなある日。
「失礼します。見学の件でお世話になります、山田です」
受付に顔を出したその人を見た瞬間、真奈美の時間が止まった。
(嘘……)
講演会で見た姿そのままの青年が、目の前に立っていた。あのときより少しだけ緊張した面持ちで、しかし、やはりあのやわらかな雰囲気を纏っている。
「……こんにちは、藤田と申します」
平静を装いながらも、声がかすかに震えた。自分の名前を名乗った途端、彼の顔がわずかに驚いたように変わる。
「藤田さん……講演会で、少しお話ししましたよね?」
やっぱり覚えていた。その事実に胸の奥がざわめいた。
「はい……あのときは、少しだけ」
「その“少し”が、ずっと印象に残ってました」
そう言って涼太は、照れくさそうに笑った。
(なに、この感情……)
年下の男性に微笑まれたことなど、いつ以来だろう。年齢のこと、子どもがいること、シングルであること、そしてもう恋なんてする年齢じゃないと自分に言い聞かせてきたのに――今、胸の奥が微かに疼いている。
「……こちらでの見学、うまくいくといいですね」
「はい、できれば……ここで、働いてみたいと思ってるんです」
その一言が、なぜか真奈美の胸にじんわりと沁みた。
(なぜだろう。……あなたがここにいると思うと、私も、少しだけこの場所が好きになれる気がする)
夜。家の中は静まり返り、息子たちはそれぞれの部屋にいた。
食器を洗い終えた真奈美は、ふと手を止め、リビングに置かれた家族写真に目をやった。
そこには、亡き夫・健一と、幼かった頃の健太と亮、そして笑顔をつくる自分が写っていた。
「……この頃は、まだ希望があったのよね」
独り言のように呟きながら、胸がじんと痛んだ。
あの頃は、夫が病んでいることに気づかないふりをしていた。
怖かったから。
どう向き合えばいいのか分からなかったから。
子どもたちの前では、いつも「平気な顔」を貼りつけていた。
けれど、夜になると布団の中で声を殺して泣いた。
――母親として、間違っていなかっただろうか。
健太は一時期、学校に行かなくなった。
亮は必要以上に自分の感情を抑えるようになった。
「全部、私のせいじゃないか……」
そんな自責の念が、今もふいに押し寄せてくる。
だからこそ――
涼太の存在が、自分を不安にさせる。
「母親が、恋愛なんてしていいのかしら」
健太と亮はもう大人になりつつある。だが、自分が他の男性と心を通わせることに、彼らはきっと戸惑うだろう。
「もう、誰かの女になる資格なんて……」
そう思いながらも、心のどこかで誰かに「優しくされたい」と願っている自分がいる。
それを認めることが、こわい。
でも、それを否定することは、もうやめにしたい――。
母として。女として。
一人の人間として、これからどう生きていきたいのか。
彼と出会ったことで、真奈美は少しずつ自分に問いかけるようになっていた。
第4章:ゆっくりと近づく距離
「今日もお疲れさまでした」
その日、仕事終わりの更衣室で、涼太が真奈美にそっと声をかけた。
「……こちらこそ、お疲れさま」
笑みを返しながらも、真奈美は少しだけ戸惑っていた。
彼の声が、自分の中に入り込む感覚がある――ごく自然に、でも確かに、何かを揺さぶってくるような。
年齢の差もある。
社会的な立場も違う。
それでも、涼太は距離を詰めようとはしない。
まるで、こちらが心を開くのを、ただ静かに待ってくれているようだった。
ある土曜の午後、二人は地域の研修会で偶然顔を合わせた。
「真奈美さん、席……あ、隣いいですか?」
「もちろん」
小さな会場の片隅、プログラムが始まる前の数分間、二人は静かに話をした。
「……真奈美さんって、本当に落ち着いてますよね。なんていうか、包み込むような空気があるというか」
「ふふ……そんなこと、初めて言われたわ」
「僕、実はあまり人に頼ったり甘えたりするのが得意じゃないんです。だからかな……真奈美さんみたいな人がそばにいると、少しだけホッとするんです」
彼の真っ直ぐな言葉が、胸の奥に静かに沁み込んでくる。
それは決して恋の囁きではない。
でも、その誠実さが、逆に彼の気持ちの本気を感じさせた。
数日後、涼太が「仕事終わりに少しだけ時間ありますか?」と声をかけてきた。
「……はい、いいですよ」
二人は近くのカフェに入った。
互いに向かい合って座り、紅茶の湯気が小さく揺れる中、涼太が言った。
「僕、いまでも自分に自信があるわけじゃないんです」
「え?」
「でも、真奈美さんと話すと、ありのままでいいって、そんな気がするんです。そんな風に思える人に出会えたのは、たぶん初めてです」
真奈美は、何も言えなかった。
(私が……彼の何かを救ってる?)
そう思った瞬間、胸の奥にある過去の痛みが、ふと軽くなるのを感じた。
「……私もね、誰かにそう言ってほしかったの。ずっと」
健一との暮らしの中で、「こうあるべき」「我慢しなきゃいけない」と繰り返してきた。
母として、妻として、いつしか「女」としての自分を置き去りにしていた。
でも――
「ありがとう、涼太さん」
ようやく、言葉がこぼれた。
彼は何も言わず、ただゆっくりと頷いた。
その日、家に帰ってから真奈美は久しぶりに鏡の前に立った。
歳を重ねた肌。目元の細かいシワ。
けれど、その奥にあるものは、決して色褪せてはいなかった。
「……もう一度、生き直してもいいのかしら」
胸の奥で、ほんの小さな芽が、そっと芽吹こうとしていた。
第5章:遅咲きの花
春が過ぎ、紫陽花が色づき始めた頃――
真奈美は、自分の心が今までとは違うリズムで動き始めているのを感じていた。
涼太と交わす会話。
職場でのふとした笑顔。
そして、たまに視線が重なる瞬間。
それは決して激しい感情ではない。
けれど、ひたひたと静かに寄せる波のように、彼女の心を揺らし続けていた。
ある夕方、職場を出ようとしたとき――
涼太がそっと声をかけた。
「……ちょっとだけ、歩きませんか?」
断る理由が見つからなかった。
いや、どこかで待っていたのかもしれない。
並んで歩いた道。
空は淡い茜色で、街の騒がしさも、どこか遠くに感じられた。
「……この道、気持ちいいですね」
「ええ、よく息子たちと通ったわ。あの頃は……もっと慌ただしかったけど」
「そうなんですね」
少しの沈黙。
そのあと、涼太は静かに口を開いた。
「……真奈美さん。僕、本当はずっと言いたかったことがあるんです」
その言葉に、彼女の心が一瞬、凍ったように止まった。
「最初にお会いした講演会の日、僕はすごく迷ってたんです。自分が何をしたいのか、自分には何ができるのか……。でも、真奈美さんが何気なく話してくれた言葉が、ずっと胸に残っていて」
「私……そんなに大したこと、言ってないと思うけど」
「いいんです。特別な言葉じゃなかった。だけど、そこに優しさがあった。ちゃんと、聞いてもらってるって思えたんです」
涼太の声は、飾り気がなく、ただ真っ直ぐだった。
その言葉を聞いて、真奈美の胸に何かがあふれた。
ずっと、そうしてほしかった。
自分の存在を、誰かに「見ていてほしかった」。
妻としてでも、母としてでもなく――
ひとりの「女」として、誰かの心に届いていたかった。
でも、それを口にするには、長すぎる時間が流れすぎていた。
「……私ね、涼太さん。ずっと思ってたの」
「はい?」
「私は……誰かに選ばれるような存在じゃないって。もう歳だし、子どももいて、人生の半分以上を、母として生きてきたから」
声がかすれる。
でも、止められなかった。
「……恋なんて、もうしないって思ってた。してはいけないって、思ってたのかもしれない。だけど……」
真奈美は、顔を上げた。
夕陽が彼女の頬を優しく照らしていた。
「でも、あなたと話すと、少しだけ……心が楽になるの。誰かに甘えていいんだって、少しだけ、思えるのよ」
涼太はゆっくりと頷いた。
何も言わず、ただ、彼女の言葉を全て受け止めていた。
そして、そっと言った。
「僕は……真奈美さんと一緒に、歩いていけたらって思ってます」
心が大きく、ふるえた。
その夜、真奈美はひとり、眠れぬまま布団の中にいた。
(私が……誰かに必要とされている?)
心の奥の奥に、小さな灯がともった。
それは、長い冬を越え、ようやくほころび始めた花のような――
遅すぎるかもしれない、けれど確かな「春」の兆しだった。
「……ありがとう、涼太さん」
彼にはまだ届かないその言葉を、心の中で何度も繰り返した。
第6章:ふたたび愛を知る
夕暮れが静かに街を染めていた。窓の外には、柔らかなオレンジ色の光が差し込み、真奈美の職場の事務室も、どこかほんのり温かい色に包まれていた。
「今日も、お疲れさまでした」
涼太が控えめに微笑み、彼女の隣のデスクにそっと一礼する。その姿はもう見慣れたもののはずだったが、真奈美はふと、胸の奥に小さなざわめきを覚えた。
(……なんで、こんなに自然にそばにいられるんだろう)
若い頃なら、恋の始まりはもっと劇的だった。高鳴る鼓動、無邪気な期待、時には嫉妬や不安すらも刺激のひとつとして感じていた。けれど今、涼太と過ごす時間は、静かで、穏やかで、傷の癒えるような感覚があった。
「今度、よければ一緒に食事でもどうですか?」
その言葉を聞いた瞬間、真奈美の心は一瞬、時間が止まったように感じた。
(……食事? それだけ?)
それだけなのに、なぜこんなに心が揺れるのだろう。返事をしようとして、言葉が喉の奥でつかえた。
「……ありがとうございます。でも……」
口から出たのは、またもや距離を取るための言葉だった。心のどこかで、まだ恐れている自分がいた。
(私は……こんな私でも、誰かと向き合っていいの?)
夫・健一が亡くなってから、真奈美は母としての役割にすべてを費やしてきた。「女としての自分」は、とうに閉じ込めてしまったつもりだった。
家では、健太と亮が微妙な距離で彼女を気遣いながらも、何かを抱えているのがわかる。彼らはまだ、父の影を引きずっている。そんな中、自分だけが新しい幸せを手に入れてもいいのだろうか――そんな罪悪感が、胸を締めつけた。
涼太は、そんな真奈美の沈黙を責めることはなかった。ただ優しく頷き、「無理しないでくださいね」と、そう言って立ち去った。
帰宅後、洗面台の鏡を見ながら、真奈美は自分の顔をじっと見つめた。いつからだろう。自分の顔を「女」として見なくなったのは。
ふと、涼太が見せたあの優しい笑顔を思い出す。
(あの人の言葉には、あたたかさがある……怖さもある。でも、私の中に生きていたいって気持ちを呼び起こしてくれる)
その晩、真奈美は久しぶりに日記を開いた。
「誰かと、もう一度向き合うことが、こんなに怖くて、こんなに愛おしいなんて、知らなかった」
ページを閉じた時、ほんの少しだけ、自分自身を許せた気がした。
第7章:家族という壁
「……お母さん、最近よく笑うね」
夕食の支度をしていた真奈美は、ふいにかけられた亮の言葉に手を止めた。
(え……今、何て?)
振り返ると、亮は湯気の立つ味噌汁の鍋を見つめながら、まるで何気ない会話の一部のようにそれを言っただけだった。
「そうかしら?」
「うん。……涼太さんと会ってからかな」
その名前に、心臓が一瞬跳ねるのを感じた。
「……別に、何もないわよ」
そう返した自分の声が、妙に冷たく響いたのがわかる。
亮はそれ以上何も言わず、静かに食卓の準備に戻った。けれど、真奈美の中では波紋が広がっていた。
(何もない……本当に、そう言い切っていいの?)
あの日以来、涼太とは何度か仕事帰りに立ち話をするようになった。特別なことを話しているわけではない。でも、その一言一言が、真奈美にとっては確かなぬくもりになっていた。
ただ――
それを「家族」に話す勇気は、まだ持てなかった。
夕食のあと、片付けをしていると、今度は健太が口を開いた。
「母さん」
「何?」
「……あの人と、付き合ってるの?」
箸の音が止まり、キッチンの空気が一瞬にして冷たくなった気がした。
「付き合ってるだなんて、そんな……」
「じゃあ、どういう関係なの?」
真奈美は目を伏せた。
(どうして……私は何も悪いことをしていないのに、こんなに苦しいの?)
「ただの……知り合いよ。職場の人」
言い訳のように聞こえる自分の声が、悔しかった。
「お父さんが亡くなってから、もう何年経ったと思ってるの?」
「……十年以上」
「だったら、母さんが誰かと……もう一度人生を歩んじゃいけない理由なんて、ないと思わない?」
その声は、亮だった。
健太は黙ったまま、テーブルの端をじっと見つめていた。
真奈美は二人の息子を見て、胸が締めつけられる思いだった。彼らは、自分のためにずっと何かを我慢してきた。自分の幸せより、母を守ることを優先してきた。
だからこそ、彼らに「誰かを好きになった」とは言えなかった。
(私が幸せになれば、誰かが傷つくんじゃないか)
そんな思いが、ずっと心に巣くっていた。
でも、同時に――
(私の人生は……まだ、終わっていない)
夜、布団に入っても眠れなかった。
静かな部屋。聞こえるのは時計の針の音だけ。
(母親として、妻として……私はもう十分に役割を果たしてきたんじゃないだろうか)
(もしも……一人の女として、もう一度愛されても、いいとしたら?)
涙がにじんだ。
それは悲しみの涙ではなく、許されたいと願う心の奥の声だった。
誰に? 家族に? 世間に?
いや、自分自身に。
(私は、私を許してあげたかったんだ)
真奈美は、ゆっくりとまぶたを閉じた。
目を閉じると、浮かんできたのは、あの穏やかな笑顔。
――涼太。
彼の隣に立つ自分を、ほんの一瞬、想像してみた。
それはあまりにも自然で、あたたかくて、そして――どこまでも優しい風景だった。
第8章:揺らぎの先にある答え
「今夜、少しだけお時間いただけますか?」
その日の午後、休憩室での何気ないやりとりの中で、涼太がそっと口にした言葉だった。
真奈美は、一瞬戸惑いながらも、静かに頷いた。
(何を話すのかしら……もしかして……)
心のどこかが騒がしくなる。普段通りを装ってはいたものの、午後の仕事中、何度も胸の奥がざわついた。
勤務終了後。
誰もいなくなった駐車場の片隅。まだ少し肌寒い春の夜風に吹かれながら、二人は車の前で向かい合った。
涼太が、少し視線を落としながら口を開く。
「真奈美さんと出会ってから、自分でも驚くほど、自分の気持ちが変わっていくのを感じてました」
真奈美は黙って耳を傾ける。
彼の声は、震えているようにも聞こえた。
「ずっと、恋愛なんて自分には無縁だって思ってたんです。自信もなかったし、誰かの人生に関われるほど立派でもないと思ってた。でも……」
彼は真奈美の目をまっすぐに見た。
「あなたと話していると、もっと誰かのために生きたいって思えたんです。あなたの強さや優しさ、そして……その奥にある、静かな痛みに気づいたとき……心が動いたんです」
真奈美の目の奥がじわりと潤んだ。
(どうして、この人は……こんなにも私のことを、ちゃんと見てくれるの?)
「僕は、あなたと……一緒に生きていきたいと思っています」
静寂が降りる。
その言葉を、彼はすべての飾りを捨てるように、真っ直ぐに告げてきた。
真奈美は、何かを言おうとして、声にならなかった。
(こんな日が、来るなんて思ってなかった)
50代という年齢。
妻としても、母としても、もう十分すぎるほど生きてきた。
だけど一人の女として、誰かに選ばれること。
誰かを選ぶこと。
それはずっと、自分に許してこなかった未来だった。
「……私、母親なのよ」
やっとの思いで絞り出した声。
「子供たちもまだ完全に自立してるわけじゃない。今さら誰かと一緒になるなんて……きっと、反発されるわ」
涼太は静かに頷いた。
「わかっています。だから、無理にとは言いません。ただ……どんな形であれ、僕はあなたと過ごす時間を大切にしたい。あなたがどんな決断をしても、受け止める覚悟はあります」
その言葉の一つ一つが、真奈美の心を揺さぶった。
(この人は、本気なのだ)
しばらくの沈黙のあと、真奈美は、ようやく絞り出すように言葉を返した。
「……ありがとう。そんなふうに言ってくれて、嬉しい」
「……でも、少しだけ……時間をちょうだい」
涼太は深く頷いた。
「もちろんです。待ちます。何年でも、何度でも」
その一言が、胸にしみた。
(私は……また、恋をしている)
帰り道、車の中で流れていたラジオの音楽も、窓の外に過ぎる街の灯も、まるで違う世界に見えた。
第9章:それでも、前を向く
「お母さん、本当に……その人と付き合ってるの?」
リビングに沈黙が落ちた。
健太の低く押し殺した声が、その空気をさらに重くした。
真奈美は、息を詰めながら頷いた。
亮は黙って天井を見上げ、健太は拳を膝の上に握りしめていた。
――この瞬間が来ることを、彼女はどこかで恐れていた。
「お父さんが死んで、どれだけ時間が経ったと思ってるんだよ……」
「もう10年よ、健太」
そう答えた自分の声が、あまりにも冷たく響いてしまったように感じて、すぐに後悔した。
「……そんなに簡単なことじゃない」
健太の声は怒っているというより、泣きそうだった。
「俺たちにだって……父さんの記憶がある。なのに……」
真奈美は、静かに目を閉じた。
(わかってる。あなたたちにとって、父はただのアルコール依存の男じゃなかった。…それでも、大切な父親だった)
「ねえ、健太。私ね、もうずっと母親でいようと頑張ってきたの。あなたたちのために、恋愛もしないって決めてた。再婚なんてありえないって、本気で思ってた。でも……」
言葉が詰まる。
「……でも、人は一人で生きていけないのよ」
涙が頬を伝った。
「私だって、誰かに寄りかかりたくなる夜があるの。誰かに『おかえり』って言ってほしい瞬間があるの。…そんな気持ち、持っちゃいけないの?」
亮がそっと顔を伏せた。
「俺……正直、驚いた。でも、なんとなく気づいてた。涼太さんとお母さん、普通の関係じゃないって」
「亮……」
「ただ、ちゃんと話してくれてよかった。今は……少しずつ理解したいって思ってる」
真奈美は、何も言えず、亮の言葉を噛み締めた。
健太は黙ったまま立ち上がり、部屋を出ていった。
扉の音が重たく響いた。
(あの子には、時間が必要なんだ)
それでも、亮の言葉に救われた気がした。
夜、涼太からLINEが届いた。
「大丈夫ですか?」
真奈美は、しばらく画面を見つめた後、こう打ち込んだ。
「大丈夫じゃないけど、大丈夫になりたいって思ってる」
数秒後に返ってきたメッセージ。
「あなたがどんなときでも、自分で自分を大切にできるように。俺は、あなたの隣にいます」
画面の文字がぼやけた。
「……ありがとう」
声に出さずに呟き、そっとスマホを胸に抱いた。
過去は消えない。
家族の傷も、簡単に癒えるわけではない。
けれど。
それでも、人は前を向ける。
遅咲きの恋は、まだ満開ではない。
でもその蕾は、確かに春の風に揺れていた。
最終章:新たな家族のかたち
冬の陽射しが、真奈美の部屋のレースカーテン越しにやわらかく差し込んでいた。
温かさの中に、どこか冷たさが残る朝。
けれど心は、不思議と穏やかだった。
日曜日。
キッチンからは、コトコトとスープを煮込む音が聞こえている。
リビングのテーブルには、亮が買ってきた花が飾られていた。
健太はまだ寝室にいるが、今日は「少し考える時間がほしい」と自分から言ってくれた。
――この数週間で、何かが確実に変わり始めていた。
涼太は、週末になると自然に家へ来るようになっていた。
でも、それを誰も責めなかった。
無理をしないこと。焦らないこと。
それが、真奈美と涼太の共通のルールだった。
その日、真奈美はゆっくりと息を吸い込んでから、テーブルに小さな箱を置いた。
「何それ?」
リビングに入ってきた亮が、不思議そうに尋ねた。
「……結婚指輪。まだ誰にも見せてなかったのよ」
「え? もう決めたの?」
「ええ。来月、籍を入れるの。……ふたりで話し合って、ようやく決めた」
亮はしばらく沈黙したあと、小さく微笑んだ。
「じゃあ、俺も……ちゃんと祝うよ。母さんの人生なんだもんね」
胸の奥が、じんわり熱くなった。
「ありがとう……亮」
その瞬間、健太がゆっくりとドアを開けて現れた。
「……俺も、行っていい?」
真奈美は、思わず顔を上げた。
「式とか披露宴じゃなくて、ささやかな食事会にするって言ってたろ。だから……参加してもいいかなって」
「……もちろんよ」
その声は、震えていた。
でも、確かにそこには温もりがあった。
真奈美の目には、涙が溢れていた。
「あなたたちがいてくれるだけで……私、もう十分幸せよ」
涼太は、静かにそばに歩み寄り、真奈美の手を握った。
「家族って、時間をかけて育っていくものなんですね」
「うん……そうね。血のつながりだけじゃない。選び合って、信じ合って、支え合っていくものなのね」
春の予感が漂う午後、四人の笑顔がひとつのテーブルに並んだ。
かつて傷つき、沈黙しかなかった家族に、ようやく光が射し始めていた。
遅咲きの恋。
その花は、ようやく満開を迎えた。
そして、
――「新たな家族のかたち」が、ここに生まれようとしていた。
あとがき
『遅咲きの恋 ―真奈美の章―』は、「年齢を重ねたからこそ、もう一度恋をすることの意味」を問いかける物語です。
この物語の根底にあるのは、「女性としての自己否定」と「母としての役割に縛られた人生」。
真奈美はその間で揺れ動きながらも、自分自身を再発見し、やがて人生の後半に咲く愛へと向かっていきます。
誰かのそばで生きること。もう一度心を開くこと。
それは決して若さだけの特権ではない。
読者のあなたが、真奈美の心の揺れに少しでも共感していただけたなら、この物語は意味を持つのだと思います。
あなたの遅咲きの花が、どうか優しく咲きますように。
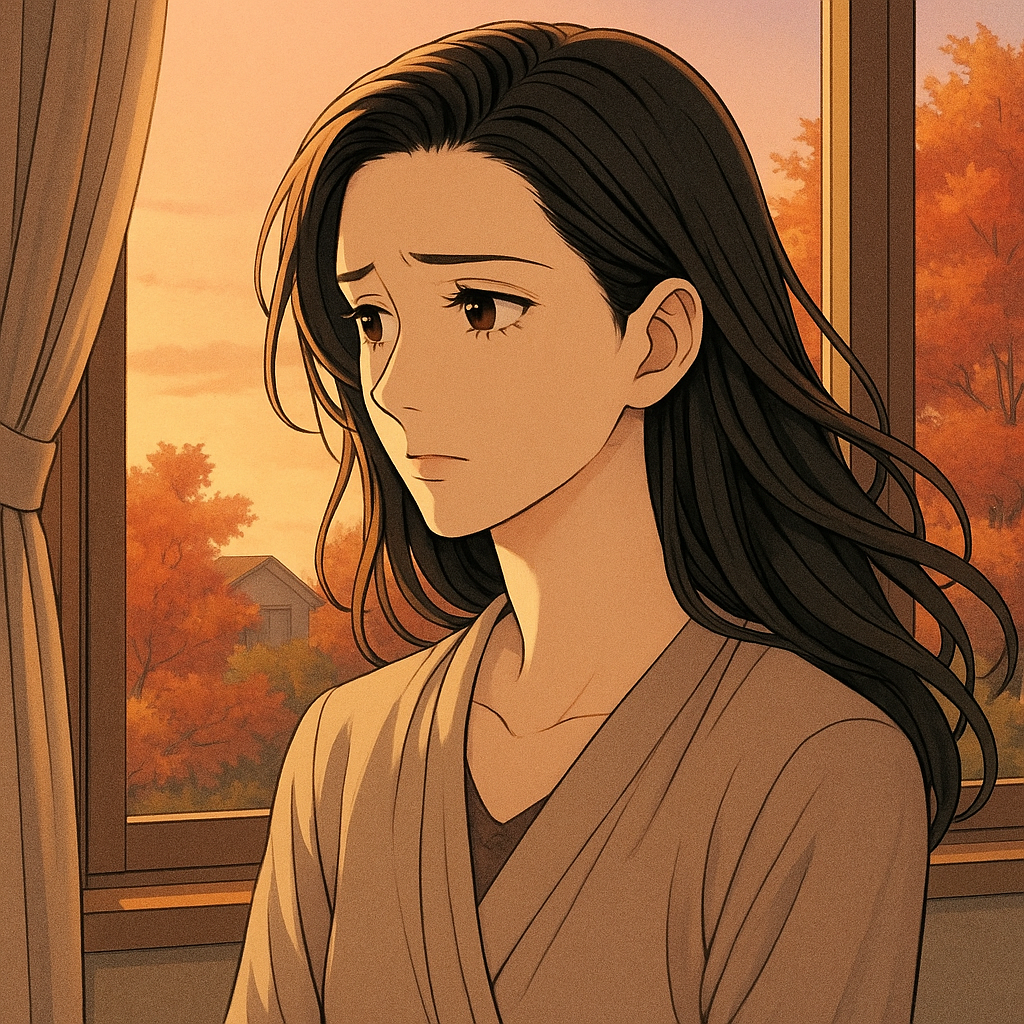


コメント ご感想や応援の言葉は、次回作へのエネルギーになります! あなたのひとことが、作品を育てます